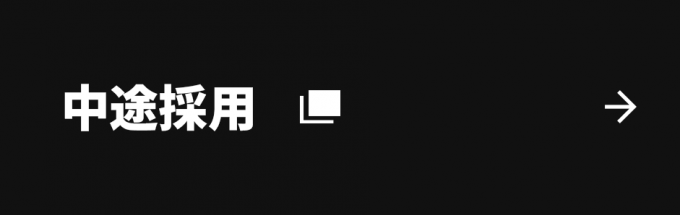法律を使いこなすビジネスマンとして、
能動的な法務部が企業の成長を
「守り」で支える

業界日本一を目指すオープンハウスグループの成長を支えているのは、攻めの営業だけではありません。顧客の安全を守り、会社のレピュテーションリスクを回避し、事業部が前向きに挑戦できる環境を整える法務部の存在が、グループ全体の推進力を支えています。月100件以上の相談に対応しながら、「事務屋にならない」という信念のもと能動的に組織を変革する法務部のお二人に、仕事への思い、そして覚悟を語っていただきました。
(2025年10月に取材)
記事サマリー
- 法務部は月100件以上の相談に対応し、トラブル解決と予防の両面で組織を支える
- 相談しやすい環境づくりと、社員を否定しない姿勢を徹底
- 事務作業にとどまらず、事業部間の調整役として能動的に動く
- 業界のオピニオンリーダーとして、正しい法的判断を不動産業界全体に広げたい
この記事に登場する人

大桑 弘充
管理本部法務部 上席課長。2013年1月に中途入社し、法務部一筋13年。法政大学法学部卒業後、法律事務所での勤務を経て入社。トラブル対応、反社チェック・与信管理、個人情報保護など幅広い業務を担当。2015年に間接部門MVP受賞。上場前から現在まで、会社の成長とともに法務機能を進化させてきた。

遠嶋 肇
管理本部法務部 上席課長。2019年8月に課長職で中途入社。同志社大学法学部卒業後、不動産業界で法務を担当。不動産トラブル全般、訴訟対応、契約書審査など、売買・仲介・設計・施工・リフォームと幅広い法務経験を持つ。2024年10月に上席課長に昇格。難しいクレーム案件でも前向きな対応を心がける。
目次
相談しやすさを追求し、社員の判断を後押しする
―お二人は中途で入社されていますが、それぞれの入社時期と、現在の法務部での業務内容を教えてください。
大桑: 私は2013年に上場準備のタイミングで中途入社し、現在では数少ない上場前の会社を知る社員の一人です。当時の社員数は約500名。2名でスタートした法務部も、現在は10名を超える体制となりました。
私が担当しているのは、裁判対応、反社会的勢力との取引を防ぐための反社チェック、個人情報保護対応、社内書類の作成など法務業務全般です。また、社内から相談窓口を通じて社内から寄せられる相談への対応や、契約書のチェック、各種書類の審査も並行して行っています。
遠嶋: 私は前々職、前職で不動産業界の法務を経験後、2019年8月に中途入社しました。現在は、各事業部やグループ会社からの不動産関係のトラブル法律相談、契約書審査を中心に、大小さまざまな案件を担当しています。
―法務部のミッションや役割を教えてください。
大桑: コンプライアンスが社会的に重視される中、法務部では社内のコンプライアンス体制を強化し、顧客満足度の向上を目指しています。
発生したトラブルに対しては、上場企業として社会的に理解を得られる現実的な解決策を導くことはもちろんですが、それ以上に再発防止策の徹底に最も力を入れています。同じ過ちを繰り返さないことが重要なんです。
遠嶋: 個別の相談対応に加えて、相談の母集団を形成する役割も担っています。日々寄せられるさまざまな相談やトラブルの内容を収集・分析し、その中から見直すべき手続きや仕組みを抽出しています。例えば、「この手続きに問題があったためにこの現象が起きた」という因果関係を明確に書面化したり、不要な手続きを削除して後続のフローを簡素化したりといった改善です。発生するトラブルのたびに根本原因を探り、議論を重ねながら、より精度の高い仕組みづくりに取り組んでいます。
―日々の業務上、コミュニケーション面で工夫されていることはありますか。
遠嶋: 最も重視しているのは、相談のしやすさです。ミスをしてトラブルを起こした社員に対して、詰問するような態度で接してしまうと、本人の精神的負担が増してしまいます。相談しやすく、頼ってもらいやすい雰囲気をつくることに注力しています。
大桑:同感です。まず相談してくる社員を否定しないことは大事ですよね。加えて、入社時から常に自席にいるように心がけています。私が入社したのは法務部ができて間もないころでしたので、いつも席にいればみんな話しかけに来やすいだろうと考えました。
もう一つ、自分の意見を明確に伝えることも重視しています。相談に来る社員の多くは、判断に迷い、決めかねている状況です。そこで少し後押しすると、「確かにその方法がありましたね」と前向きになっていただけます。その時に大きなやりがいを感じますね。
また、具体例を交えて伝えることも意識しています。例えば、「以前、◯◯さんがこういうことをして失敗し、その結果こう叱られました」というように、実際の事例を示すと理解していただきやすいんです。抽象的な話だけではなかなか伝わりませんから。

能動的に動く「事務屋にならない」法務部が組織を変革する
―他社を経験されたお二人から見て、オープンハウスグループの法務部にはどんな特徴があると感じますか。
大桑: 入社時から「事務屋にならないように」と繰り返し言われてきました。事務作業だけをこなすのではなく、自分の考えを持ち、存在意義を示してほしいということです。メーカーなどの法務部では、契約書のチェックだけで業務が完結したり、事務作業が中心だったりというケースは少なくありません。しかし、私たちは極めて能動的に動いています。私たちが提案した施策が、他部署から協力を得られて実現することもあります。事務作業にとどまらず能動的に動けることが、他社との大きな違いです。
遠嶋: 事業部同士で見解が対立した時、その調整役を依頼されることもあります。いわば裁判所のような役割で、事業部同士が直接対立するとシリアスになりすぎるため、法務部が中立的な立場で間を取り、調整に入ります。
もう一つの大きな特徴は、相談の案件数が極めて多く、多様な過去の事例が蓄積されていることです。事業部から「こういうことがあったのですが、法務部で過去に類似案件はありませんか?」と尋ねられると、ほぼ確実に参考になる事例が見つかります。
―その事例の蓄積は、どのような仕組みで実現されているのでしょうか。
大桑: 案件が上がりやすい風土と、社内ポータルサイトに構築した「法務部ウィキ」の存在が大きいです。Googleフォームを使って簡単に問い合わせができる環境を整備しており、このフォーム経由で月に80件から100件ほどの相談が社内から寄せられ、契約書のチェックもここに集約しています。
法務という仕事は他社では属人化しやすい傾向がありますが、私たちは相談フォームで情報を可視化し、誰でもアクセスできるようにすることで、属人化を防いでいます。過去の案件が蓄積されていることも大きいです。法務部ウィキに法律相談の件数も記録されていますし、スプレッドシートのデータを見れば、過去にどう対応したかが分かります。
遠嶋: 法務部ウィキは2021年から本格的に運用を開始しました。それまでは、メール、チャット、口頭など、相談方法が統一されておらず、宛先や資料の添付方法にもルールがありませんでした。専用の相談フォームを導入してからは、相談する側にとってもルールが明確になり、情報の整理が一気に進みました。すべての相談がアーカイブ化され、組織の財産となっています。

―オープンハウスグループの良さはどのようなところにあると感じますか?
大桑: 徹底力の高さにあると感じます。目標達成志向が強く、それが組織全体に浸透していることは大きな強みです。
私が入社を決めた理由は、上場準備というワクワク感と、わずか3〜4日の間に2回の面接を経て採用が決まるという選考のスピード感でした。その速さに、この会社の本気度を感じました。一方で、入社前はあまり事前情報がなく、初日に全体朝礼があると聞いて、「30人ぐらいの前で管理本部のメンバーに挨拶する程度かな」と思っていたんです。ところが実際には、約500名もの社員が集まっていて、その一体感と熱量に圧倒されました。本当にすごい雰囲気で、正直「聞いてないですよ!」と思いましたね(笑)。
その時に印象的だったのが、社長の言葉が社内に驚くほど早く浸透したことです。当時の社長が「お客さまをお待たせしないよう、受付には走ってお迎えに行くように」とお話しされたのですが、朝礼が終わってわずか15分後には、そのメッセージが全社に行き渡り、実際の行動として徹底されていました。普通の会社であれば聞き流して終わるようなことが、即座に共有・実践される。その徹底力を目の当たりにして、これはしっかりなじまないと、と気が引き締まりました。
遠嶋: 私は、各部署が依頼を真摯に受け止め、確実に遂行してくれることに良さを感じます。どこの部署にも属さないような案件が法務部に回ってくることもありますが、「この件はこの部署で対応するのが適切ではないか」と話を戻した時に、責任を持って引き受けてくれるんです。
また、投げたボールを受け止めてくれる人が多いということにも、オープンハウスグループの良さを感じます。前職ではボールを投げても誰も受け取ろうとしないような雰囲気がありましたが、ここでは全く違います。社員一人ひとりが自分ごととして課題に向き合う意識が極めて強いと感じています。
私が入社した2019年当時は、すでにオープンハウスの知名度も高く、社風もある程度想定していましたが、実際に働いてみると管理本部はとても穏やかで、想像以上にマイルドな雰囲気でした。ただ、明らかにこれはすごいなと思ったのは、表彰式や朝礼で見た社員の士気とテンションの高さです。あの時の社員のエネルギーには本当に驚きました。
最近では、管理本部の若手も「営業部門に負けないように」という意識を持って、朝礼での声の出し方にも力を入れています。その姿勢も、オープンハウスグループらしさの表れだと感じます。

▼コーポレート職へのエントリーはこちらから
新卒採用の方はこちら 中途採用の方はこちら
顧客の安全を最優先に、レピュテーションリスクを回避する
―法務部における「守り」の業務について、具体的にどのような取り組みをされているのか教えてください。
大桑: 各事業部から寄せられる法律相談や契約書審査が、いわゆる「守り」の業務に当たります。トラブル対応や反社チェックなども行い、コンプライアンス面で問題が生じないよう日々取り組んでいます。また、レピュテーションリスク――つまり会社の評判が損なわれないよう常に注意を払っています。
しかし、最も優先しているのは、お客さまの安全です。費用の多寡にかかわらず、お客さまの住宅に不具合があり危険が及ぶ可能性がある場合、あるいは法令に適合しない場合には、必ず是正するという方針を貫いています。
まずお客さまの安全を第一に考える姿勢を徹底することで、結果的に会社のレピュテーションリスクも自然と回避できると考えています。何よりも、お客さまに不安を与えないことが大切です。
遠嶋:実際に対応している従業員の精神的負担を軽減することも重視しています。どのように切り抜けていくか、どう対応していくか。場合によっては対応しないという選択も含めて、方針を決定し提案することが私たちの役割です。重大なトラブルや案件を抱えると、担当者は精神的に追い詰められます。前職の不動産会社では、担当者に責任が集中し、退社してしまうケースもありましたが、そのような事態を防ぎたいと思っています。全員で協力すれば解決できることですから。
難しいクレーム案件の対応でも、深刻な事態以外は暗い雰囲気にしないよう心がけています。基本的には、人が亡くなる以外は笑い事に変えても構わないぐらいの根性でやらないといけないと考えています。
―法務部の「守り」は、オープンハウスグループにどのような貢献をしているとお考えですか?
大桑:レピュテーションリスクをかなり回避できていると考えています。とはいえ、リスクマネジメントは答え合わせができないものです。「これはやめましょう」と判断して実行しなかった場合、それが正しかったのかどうかは検証はできません。
ただ、ごくまれに答え合わせができる瞬間があります。例えば10年ほど前、ある団体から戸建て物件を宿舎として利用したいという申し出がありました。しかし、周囲にお住まいのお客さまへの影響を考慮し、お断りしたんです。当時は営業部から不満の声も上がりましたが、のちにその団体が社会問題化し、あの時に判断を誤らず本当に良かったと実感しました。
何かを実行して失敗した時に、「なぜそれを行ったのか」と問われて説明できないようなことはそもそも実行すべきではないというのが、私の判断基準の一つです。行動には常に明確な理由を持ち、説明できることが重要だと考えています。
遠嶋: 私は、社員が安心して働ける環境づくりにも貢献できていると感じています。そして、その根底にあるのは人間力、すなわち法律を使いこなすビジネスマンとしての総合力だと思います。それこそが、私たちが生き残り、会社を成長させていく源だと考えています。
業界のオピニオンリーダーへ。AIと人間の協働で実現する未来
―業界日本一を目指す上で、今後、法務部が担う目標や成長ビジョンについて教えてください。
大桑: 今後の法務部は、人員を増やしAIを活用して組織化することで、専門性の属人化をなくしていきたいと考えています。また、法律知識のない初心者が配属されても、短期間で一人前として活躍できる環境づくりを目指しています。業務のマニュアル化を進め、未経験者でも一年程度で十分に業務をこなせる仕組みが、着実に整いつつあると感じています。
メンバーの専門性を保持しつつ、法律のビジネスマンとして育成していく中で、法律知識以上に、コミュニケーション能力やリーダーシップ、企画・行動力といった能力がより重要になってきます。これらを主体的に発揮できる人物を育てていきたいですし、自分もそうなりたいと思っています。
遠嶋:会社が成長すれば、守りの部分も強化する必要があります。法律の専門家だけを採用し続けるというやり方では、もはや追いつきません。一般的な法律業務については、すでに生成AIの方が優れている部分もあります。だからこそ、私たちはAIに対抗するのではなく、AIを活用してビジネス課題を解決できる人材を育成することが重要です。
現在、社内からは「AIがこう回答していますが正しいでしょうか」という問い合わせも増えていますが、確認すると約2割は誤った内容です。改正済みの法律情報や世間の誤解など、ネット上には古くて不正確な情報も散見されます。生成AIは確かに正確でスピードも速い一方、まだ完璧ではありません。最終的に判断するのは人間ですから、AIでは対応しきれない部分を見極め、人と向き合う業務で付加価値を発揮することが、私たち法務部の役割だと考えています。
大桑: また、不動産業界のオピニオンリーダー的な存在になりたいとも考えています。周囲の不動産業者から、「オープンハウスグループが使用している書類の書式であれば間違いない」「オープンハウスグループがこう動くなら自分たちも同じように動く」と業界に評価されるようになりたいと考えています。

―法務部を志望される方や、オープンハウスグループへの入社を検討されている方へメッセージをお願いします。
大桑: コミュニケーション能力がある方、リーダーシップを発揮できる方、そして企画力と行動力を持つ方を求めています。そして、新しい経験を積みたいのであれば、オープンハウスグループを選ぶことを強くお勧めします。さまざまな新しい経験の場を与えてもらえるので、本当に飽きることがありません。
会社が成長しているため、守りの法務であっても極めて刺激的なのです。守りと聞くとルーティンワークを想像されるかもしれませんが、成長企業の法務は違います。新しい課題が次々と生まれ、それに対応していく過程で、常に新しい経験を積むことができるんです。
新規事業は「攻め」の側面がありますが、その新規事業を法的に「守る」のが私たち法務部の役割です。例えばアメリカ進出の際には、アメリカの法律を調べたり、現地の弁護士と日本をつないだりする業務を担当しました。新規事業自体は攻めであっても、私たちが関わる部分は、その事業を実行するための守りの部分です。
法務に関して新卒未経験や法学部出身でなくても問題ありません。法務部に入る社員にも伝えていますが、私たちはあくまでも法律関係の仕事をするビジネスマンです。法律知識だけを追求する必要はなく、専門知識を極限まで掘り下げることはしません。それよりも、社員に対して的確な提案ができることの方が重要なのです。法律は共通言語として理解できればよく、分からなければ外部の専門家に聞けばいい。そんなビジネスマンとしての考えを忘れないようにと、常に伝えています。
遠嶋: 不動産業界は、決してなくならない業界です。人間が家に住まなくなる未来も、土地の上に住まなくなる未来も訪れないでしょう。将来を心配する必要はなく、一生をかけてエネルギーを注げる業界だと、私は若手社員に伝えています。
よく「トラブルばかり扱っていて辛くないですか」と尋ねられることがありますが、おそらく私は発生している問題そのものよりも、社員が「解決しました」とすっきりした表情を見せる瞬間に目が向いているのだと思います。問題が解決し、社員が前を向いて帰っていく姿。それが私たちのやりがいであり、原動力になっています。

守りの覚悟が、攻めの成長を支える
法務部という「守り」の役割を担いながらも、能動的に動き、事業部と協力して会社を前に進める。大桑さんと遠嶋さんの言葉からは、単なるリスク回避にとどまらず、オープンハウスグループの成長を支えるという強い覚悟が伝わってきました。顧客の安全を何よりも優先し、社員が安心して働ける環境を整え、業界のオピニオンリーダーとして正しい法的判断を示していく。その確固たる信念が、業界日本一を目指す会社の土台を支えています。