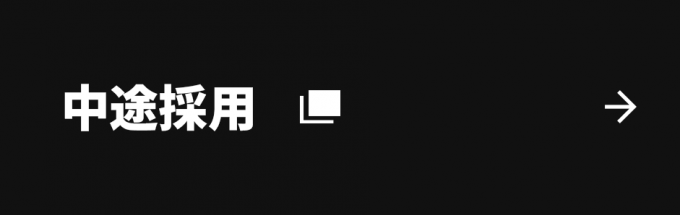赤字だったスキー場を
1年で黒字転換。
一級建築士の若手社員が「何をやるかよりも誰とやるか」で挑む地域共創の現場

建設事業部から地域共創の最前線へ——。オープンハウスグループのサステナビリティ推進部で係長を務める池田悠人さんは、赤字続きだったスキー場をわずか1年で黒字化に導き、さらに廃校活用プロジェクトにも挑戦しています。1級建築士の資格に加え、電気工事士や危険物取扱者の資格まで取得し、とにかく「何でもやる」というスタンスで地域に飛び込む池田さん。そんな彼が取り組むのは、「人・もの・仕事」を好循環に変えていく地域共創事業です。異色ともいえるキャリアの歩みと、成長企業の中で多彩な経験を積むことの魅力について伺いました。
(2025年7月に取材)
記事サマリー
- 赤字続きのスキー場を1年で黒字化、地域共創事業の最前線で活躍
- 「何をやるかよりも誰とやるか」の哲学で建設から地域共創への転身を果たす
- 1級建築士に加え電気工事士・危険物取扱者まで取得し、現場に密着する実践力
- 感動の宝探し企画とガソリンスタンド存続への使命感が示すオープンハウスの地域貢献
この記事に登場する人

池田 悠人
サステナビリティ推進部 地域共創グループ 係長。早稲田大学創造理工学部建築学科を卒業後、2021年4月にオープンハウスグループ入社。注文設計に配属後、2022年1月に渉外技術グループ技術企画課へ異動、2023年7月に主任昇格、同年10月に事業開発部へ異動。2025年4月に係長昇格と同時に部署統合により現職。現在は、「群馬みなかみ ほうだいぎスキー場・キャンプ場」と「KIRINAN BASE」(旧桐生南高校)のプロジェクト担当者を務める。
目次
1年で赤字スキー場を黒字転換。地域の好循環を生み出す使命感
ー現在所属されているサステナビリティ推進部地域共創グループについて教えてください。
サステナビリティ推進部は、2025年4月に、経営企画部の機能と私が所属していた事業開発部を統合し、地域共創とサステナビリティの取り組みを一体的に推進する体制として構築されました。企業としての成長を通じて持続可能な社会を実現していくこと。その一つが「地域共創」という考え方です。
都市部では「人・もの・仕事」が好循環を描いていますが、地方では人口減少や産業衰退によって悪循環に陥っているケースが少なくありません。この構造的課題をオープンハウスならではの実行力や突破力で解決し、地域に新しい循環をつくることを目指しています。
ー池田さんが実際に手がけられた地域共創の成果について聞かせてください。
「群馬みなかみ ほうだいぎスキー場・キャンプ場」は、まさに地域共創の原点となりました。私が参画した2023年10月時点では長期間の赤字経営に苦しんでいましたが、2024年9月期に黒字転換を達成しました。今年度も前年比で売上・利益ともに成長を見込んでいます。単なる収益改善にとどまらず、現地スタッフへのボーナス支給や昇給機会の創出により、地域への価値還元を実現することを重視しています。
もう一つの柱が「KIRINAN BASE」という廃校活用プロジェクトです。2021年3月に閉校した群馬県立桐生南高校の跡地を地域交流拠点として再生し、レンタルスペース事業や中学生硬式野球チーム「桐生南ポニーリーグ」の活動拠点として運営しています。
地域共創事業の特徴は、その波及効果の大きさです。スキー場ひとつでも、影響を及ぼす範囲は数百人から数千人規模に及びます。スキー場が廃業すれば、周辺の民宿や観光業者も連鎖的に影響を受けてしまう。そうした地域経済全体への責任を感じているからこそ、単年度の黒字化にとどまらず、持続可能な発展を目指す必要があります。
ですから、真の挑戦はこれからです。たとえば、ほうだいぎを年間を通じて楽しめるリゾートに進化させれば、さらに大きな成長が見込めます。この1年は努力することで黒字化できましたが、これからも長期的に事業を発展させるためには大きな投資が必要です。さらに売上利益を伸ばしていきながら、その戦略を構じることが、現在私に課せられている最大の課題だと感じています。

大学院に進学するより、オープンハウスで働いた方が成長できる
ー若くして重要な課題を担う池田さんですが、オープンハウスグループとの出会いについて聞かせてください。
早稲田大学建築学科に在籍していた私は、当初は王道のキャリアコースを想定していました。成績も悪くなかったため、大学院推薦を得て、ゆくゆくは大手デベロッパーへの就職が自然な流れだろうと考えてたんです。
転機となったのは、当時のオープンハウスの建設インターンシップでした。優勝チームに賞金が設定されているという情報を知り、率直に申し上げると、その賞金に惹かれて参加したんです(笑)。
しかし、インターンで人生観が変わりました。社員の皆さんの熱量が尋常ではなかったんです。自分と同年代の若い社員が、圧倒的な熱量を持って業務に取り組む姿を見て、「大学院に2年間行くより、オープンハウスで2年間働いた方が絶対に成長できる」と確信し、初日で入社を決意しました。
—建設事業部から現在の部署への転身は、どのような経緯だったのでしょうか?
入社後は建設事業部で注文住宅の設計を担当し、その後渉外技術グループで、ビジネスの基礎と1円単位のコスト意識を学びました。オープンハウスではさまざまな経験を積んだうえに建設事業部長を目指したいと思っていた私に、あるとき上長から「事業開発部に行かないか」と声がかかりました。正直、最初は何をする部署かも分かりませんでしたが、私にとって最も重要なのは「何をやるかよりも誰とやるか」です。とても前向きに受けとめて異動しました。
この価値観は私の根幹をなしています。オープンハウスの社員と働けるのであれば、どのような仕事でも全力で取り組みたいと考えています。このときも活躍している社員が多いと聞く事業開発部で、新しいことが学べると感じました。ちなみに、建設事業部での経験は現在も活かされています。設計知識はスキー場やキリナンベースの改修工事で役立ち、コスト意識は事業運営の基盤となっています。
▼建築技術職への応募フォームはこちらから
新卒採用の方はこちら 中途採用の方はこちら
—スキー場の黒字化に成功した要因は何でしょう?
黒字化の要因は複数あります。まず、スキー場経営に詳しい専門家との業務提携により、適切なアドバイスを実行に移しました。無駄なコストの見直しと適正価格への調整、そしてほうだいぎスキー場の強みである、雪質の良さや多様なコース設計を活かしたプロモーション戦略の強化です。
特にSNS戦略では、現地スタッフを「おじさんず」と名付け、Z世代の私と「おじさんず」が協力して頑張る姿をInstagramで発信しました。フォロワー数は当初の7,000人から15,000人以上と倍増し、お客様の投稿もリポストすることで、来場体験の共有と再訪促進を図りました。こうした取り組みの結果、2025年度はさらなる成長を見込んでいます。
—資格取得にも積極的だとお聞きしています。
入社2年目で1級建築士をストレート合格できたのは、意思を持って努力をした結果だと思います。これは将来、ホテル建設などを計画するうえでの基盤になると考えています。
現在も電気工事士や危険物取扱者など、業務に必要な資格を取得し、実際にみなかみ温泉街の再生プロジェクトで電気工事を自ら行いました。コストを抑えられるだけでなく、そうした現場での当事者性のある実践が地域の方々との信頼関係構築にもつながると実感しています。

変わらぬ仕事の原点「人を笑顔にしたい」を、地域共創で実践
—池田さんが地域共創事業で最も重視していることはなんでしょうか?
一番大事なのは「人」です。都心部はITやウェブ、契約書で業務が進みますが、地域は人と人との関係性を重視します。仮に価格競争力があっても、「この人との関係性があるから」という理由で取引先を選ぶこともあるんです。緊急時の対応も、人間関係があるからこそ迅速に対応してもらえる。つまり「人・もの・仕事」の好循環は、まず人から始まるのです。
また、地域の方々との関係づくりで欠かせないのが、「教えてください」という姿勢。東京から来た人間は、たとえ資格を持っていても、地域のことは分かっていないのですから、謙虚に学ぶことが不可欠です。最初は“外の人間”と一定の壁を感じることもありますが、密にコミュニケーションを取ることでその壁は乗り越えられます。実際、シーズン中は現地に常駐し、地域の方々と寝食を共にしながら信頼関係を築いてきました。
中でも印象に残っているのは、宝探し企画です。スキー場のゲレンデに、番号札を配置して、景品には来季のシーズン券やスキーグッズなど総額100万円相当を用意したところ、お客様が本当に楽しんでくださいました。
そのときの写真や動画を見返すと、今でも涙が出てきます。冬の厳しい業務もありましたが、これだけお客様が笑顔になってくれる。まさか自分が仕事で感動して泣くとは思わなかったので、忘れがたい経験になりました。これは私の原点とつながっています。高校時代から遊園地で6年間アルバイトを続け、最年少でアルバイトの指導役まで上り詰めました。「誰かを幸せにしたい、笑顔にしたい」という想いから遊園地を選んだのですが、オープンハウスでの仕事も同じです。スキー場もお客様を笑顔にする仕事ですし、キリナンベースの再生も多くの人を笑顔にできる。その想いがずっと自分の根底にあります。
—困難な局面での判断について具体例を教えてください。
最近では、近隣のガソリンスタンドの存続問題です。ほうだいぎスキー場と地元企業2社で共同経営しているガソリンスタンドがあったのですが、他の2社から廃止提案がありました。しかし、次のガソリンスタンドまで30分かかる僻地で、地域の生活インフラとして、またスキー場経営の観点からも、存続が不可欠でした。
オープンハウスグループとして、ガソリンスタンドを経営するのは異例の判断です。1年以上かけて社内を説得し続けました。最初は反対もありましたが、ほうだいぎの黒字化実績によって、社内から承認を得られたと思います。このように社内での本事業への目線も、「今年はどれだけ赤字か」というマイナス思考から「年間リゾート化をどう進めるか」というプラス思考に変化してきた手応えを感じます。

努力する人にチャンスをくれる会社で、「誰とやるか」を大切にする
—今後の目標について教えてください。
個人としてのキャリア目標は変わりません。さまざまな知識を吸収し、会社に貢献しながら、最終的には建設事業部長を目指したいと考えています。現在はスキー場経営に携わることで、建設部門だけでは得られない学びを得ることができました。今後さらに成長し、ゆくゆくは建設事業部に戻って力を発揮したいと思います。ただし、仮に営業部に異動となった場合も、迷わず営業部でトップを目指します。
もう一つの目標は、地域共創の横展開です。現在はスキー場、キャンプ場、廃校活用とそれぞれ1拠点ずつですが、成功モデルを横展開し、より多くの地域で好循環をつくり出したいと考えています。
—オープンハウスグループの魅力と入社希望者へのメッセージをお願いします。
オープンハウスグループの最大の魅力は、努力している人材にチャンスが与えられ、適切に評価されることです。事業拡大に伴い様々なポジションが生まれ、私が入社した頃にはなかった廃校活用事業やホテル事業も始まっています。しかし、そのチャンスを掴めるのは、現在の職務で結果を出し、努力を継続している人材のみです。そうした人材に積極的にチャンスを提供してもらえるのが、この会社の真の強みです。
入社を希望される方には、やはり「何をやるかよりも誰とやるか」が重要だとお伝えしたいです。長い人生ではさまざまなキャリア選択肢がありますが、オープンハウスは熱い才能が集まり、一緒に成長できる人々が多い企業です。
どんな楽しいことでも、情熱のない人とでは楽しくありません。しかし、どんな困難な課題でも、協力し合える仲間がいれば必ず乗り越えられます。オープンハウスは、一緒に成長し、高い目標を追求できる人材が集う企業であると断言したいです。

地域と共に成長する、新たなビジネスモデルを創造するオープンハウス
赤字続きのスキー場を1年で黒字転換し、地域に根ざした価値創造を実現した池田さん。その背景には「何をやるかよりも誰とやるか」という明確な価値観と、現場に飛び込む実践力がありました。単なる不動産開発にとどまらず、地域社会の持続可能な発展に貢献するオープンハウスグループの地域共創事業。そこには、新しい挑戦を恐れず、共に成長を目指す人材を求める企業文化がありました。