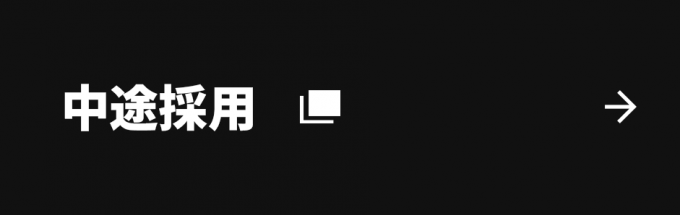都心でリーズナブルに理想の家を届ける。高い技術力と提案力を武器に難題に挑む、オープンハウスの設計士たち

日本一を目指し、急成長を遂げるオープンハウス。その成長を“商品作り”の面で支えているのが、建売住宅や注文住宅を手がける建設事業部です。グループ全体の売上の約半数を占め、都心部を中心に年間4,000棟の住宅を建築しています。
オープンハウスの家は、他と何が違うのか。強さの秘密は、どこにあるのでしょうか? 今回は、建設事業部で設計士として活躍する、田所さんと大野さんにインタビュー。お客さまとの打ち合わせからプランニング、設計、オプション提案まで担うお二人に、オープンハウスの家づくりの強みを教えてもらいました。記事の最後には、設計士のお二人がもし自分の家を建てるならここを見る!というポイントも紹介しているので、家づくりに興味のある方はお楽しみに。
記事サマリー
- 設計グループは、難易度の高い設計に限界まで挑むスペシャリスト集団
- オープンハウスの設計士は全員、複雑な「天空率の計算」ができる
- 切磋琢磨できる環境が、設計士の成長スピードを加速させる
この記事に登場する人

田所 祥子
建設事業部 設計部 注文住宅設計グループ。2019年新卒入社。入社2年目に主任、4年目でマネージャーに昇進し、6年目には係長へ昇格。現在は設計業務に加え、課員の育成や新卒教育を担う。これまでにMVP賞を2回受賞した他、オプション受注額トップも2度、獲得している。

大野 七海
建設事業部 設計部 注文住宅設計グループ。2020年4月入社。3年目で主任、4年目でマネージャー、5年目で係長に昇格。MVP賞、社内コンペ・外観マイスター、プランマイスター受賞など、数々の受賞歴を誇る。現在は注文住宅の設計と課員の育成を担当。
目次
開発事業部が仕入れた土地に設計し、図面を工事部へ引き渡す
—はじめに、お二人が所属する建設事業部について教えてください。
田所:私たち建設事業部は、開発事業部が仕入れた土地に戸建住宅を設計・建築する部署です。「設計部」と「工事部」の2つから成り、設計部が家の図面を作成し、それをもとに工事部が実際に家を建てていきます。
設計部はさらに、「注文住宅設計グループ」と「建売住宅設計グループ」に分かれています。両者の大きな違いは、設計の段階でお客さまがいるかどうか。注文住宅が、お客さまと向き合いながら、そのご要望に応じた家を設計するのに対し、建売住宅は土地と建物をセットで販売するので、購入者が決まる前に、将来のニーズを見据えて設計するのが特徴です。
—建設事業部における2人の役割と業務を教えてください。
大野:私たちは入社以来、注文住宅の設計を担当しています。オープンハウスの土地をご購入いただいたお客さまに対し、どんな家を建てたいのか直接ヒアリングを行い、土地や周辺環境、お客さまのご要望、ライフスタイルなどに応じた間取りやオプションをご提案します。そして、最終的にお客さまの理想の家を図面に落としこむのが私たちの仕事です。
田所:注文設計グループには現在、37名の設計士が在籍しています。ありがたいことに開発事業部が土地をたくさん仕入れ、その土地を営業本部がたくさん販売してくれるおかげで、設計業務は常にフル稼働で、設計士が足りないくらいです(笑)。でもすべての部署が連携して仕事を進める中、設計部で滞らせるわけにはいきません。図面を工事部へスムーズに渡せるよう、全力で取り組んでいます。

「この限られた土地に、いかにお客さまの夢を叶えるか?」可能性を最大限まで追求
—オープンハウスの家が持つ強みとは、何だと思いますか? 田所さんからお聞かせください。
田所:最大の強みは、都心駅近の狭小地に、広々とした住まいを実現できることだと思います。都心の土地は狭いだけでなく、変形地や入り組んだところにある土地、厳しい建築制限がかかる土地も多くあります。他のメーカーが匙を投げてしまうような建築難度が高い土地でも、オープンハウスはその土地に最大ボリュームの家を建てることができます。結果、土地面積が小さいので価格が抑えられ、都心の好立地でありながらリーズナブルな価格で家を提供できるんです。
—他のメーカーには建築が難しいケースでも、オープンハウスに可能なのはなぜでしょう?
田所:私たち設計グループには、都心・狭小地の設計に精通したスペシャリストがそろい、それぞれが「この限られた土地の中に、いかにお客さまの理想を叶えるか」を常に考え、可能性を最大限に追求しながら設計に取り組んでいます。
例えば、設計には「天空率」というルールがあります。すごく簡単に言うと、「建物の前に立って上を見たときに空がどれだけ見えるか」を計算し、周りの建物や環境とのバランスを考えて設計するための基準のこと。建物を設計するとき、普通は「高さ制限」というルールを用いて建物の高さを決めますが、この天空率を上手く使うと、工夫次第でより高い建物を作れる場合があるんです。
天空率を設計に活かすには、高度な専門知識と複雑な計算が必要となるため、対応できるハウスメーカーは限られています。しかしオープンハウスでは少しでも高く広く設計するために、天空率をフル活用。設計士全員が専用のCADソフトを使って精密な計算を行い、制限のある土地にフルボリュームの家を実現しています。
—そこまでやるハウスメーカーは少ないのですね。
田所:その通りです。他にも、1階を半地下のようにして空間を広げたり、日の当たりにくい土地では、あえて3階にリビングを配置して採光を確保したりといろんなノウハウを持っています。都心・狭小地での豊富な経験を活かした柔軟なプランニングも、オープンハウスならでは。建築基準法以上に厳しく設定されている社内基準を遵守しながら、狭さを感じない豊かな住空間を生みだすのが得意です。

—では、大野さんは、オープンハウスの強みとは何だと思いますか?
大野:田所さんと同意見ですが、もう1つ挙げるなら「価格」ですね。オープンハウスの注文住宅は、最低限のベースに、間取りやオプションでカスタマイズするセミオーダー制です。ベースの価格が抑えられているぶん、内装をおしゃれにしたい、耐震性を重視したいなど、お客さまがこだわりたいところに予算をかけられるので無駄がありません。お客さまからも「他のメーカーと比較しても、トータルで価格を抑えられる」と評価をいただいています。
—セミオーダーと聞いて、「自由にできない」という声はありませんか?
大野:オープンハウスは間取りの自由度が高く、設備や機能、デザインなどのオプションも豊富に取り揃えています。お客さまには幅広い選択肢からお好みのものをお選びいただけるのはもちろん、設計士がお客さまのライフスタイルに合わせた最適なオプションをご提案し、理想の家に近づけていきます。こうした提案力の高さも、オープンハウスの設計士ならではだと思います。

設計士も成果主義。数字を追うから仕事のクオリティが上がる
—高度な設計力や提案力といったスキルを、設計グループの皆さんはどのように習得しているのでしょうか?
大野:入社後の研修もありますが、今でも日々の勉強は欠かせません。法規関連や社内の設計ルールのテストは毎月ありますし、商品知識の習得も必須です。商品は膨大にあり、しかも頻繁に入れ替わるので、常にキャッチアップしています。
そんな中、一番の学びの場は、お客さまとのやりとりです。一般的な家づくりでは営業を介してプランを進めますが、オープンハウスでは設計士が営業を兼ね、お客さまと直接やりとりを行います。ヒアリングやご提案を通して、お客さまのご要望や反応をダイレクトに受け取り、お客さまがどんなことに悩まれるのか、どんな点を重視されるのかを知ることができる。そして、その気づきを即、設計に反映できるのは、設計士にとってこれ以上ない学びです。
田所:数をこなせることも大きいですね。オープンハウスはとにかく棟数が多いので、何回でも設計にチャレンジできる機会があります。常に10組ほどのお客さまを並行して受け持ち、短期間にたくさんの経験を積めることでスピーディに成長できるので、設計士としての引き出しが増えていくのを日々実感します。
—お二人がこれまでに複数回受賞している「MVP賞」についても教えてください。
田所:MVPは、3カ月ごとに最も優秀な成績をおさめた設計士が表彰される社内制度です。評価項目は、担当件数、オプション受注額、図面の正確性、設計工期の無駄のなさ、デザイン力、お客さまアンケート……などなど多岐にわたり、項目ごとにポイントが加算・減算される仕組みです。
—設計士が数字で評価されるのは珍しいですね。
田所:オープンハウスでは、設計士も成果主義です。ポイントを稼ぐには、業務効率を上げて1件でも多くの案件を手がける、魅力的なご提案をしてオプション受注額を増やす、設計ミスを防ぐなど、全方位に注力しなければなりません。常に気を抜けませんが、数字を意識することで思考の密度が高まり、仕事のクオリティが上がります。全員のポイントがリアルタイムで確認できるので、1位を狙っているときや2位から追い上げているときは、常にチェックしていましたね。
大野:入社当初は、先輩方と同じ土俵で競うことにプレッシャーを感じてヒリヒリしていましたが、実力がついてきたら、数字を追う楽しさに目覚めました(笑)。年次に関係なくフェアに評価してもらえる環境は、モチベーションアップにつながります。他にも、「建売KING」「Order KING」など設計力を競う社内コンペもあり、切磋琢磨できる環境が、設計士全体のレベルを底上げしていると感じます。

▼建築技術職への応募フォームはこちらから
新卒採用の方はこちら 中途採用の方はこちら
—スキルを磨き続けているからこそ、難題にチャレンジできるんですね。そんな中、壁にぶつかることもありますか?
田所:もちろんあります。土地があまりに狭くてクラクラすることもあれば、お客さまのご要望と諸条件をどう折り合いをつけようかと、頭を抱えることもしょっちゅうです。でも、設計グループには37人のスペシャリストがいます。チームでアイデアを出し合うことで、突破口が見つかったり、より良いプランが生まれたりすることが多いです。難題に挑み、最適な住まいを形にする——それが、オープンハウスの設計士である私たちの仕事です。これからも技術を磨き続け、お客さまの理想の住まいを叶えていきたいですね。
オープンハウスの設計士は「家づくり」のココを見る!
ここからは番外編。オープンハウスの設計士として家づくりの最前線に立つ田所さんと大野さんから、「家づくり」で見るべきポイントを指南してもらいました!
1. その立地、将来売れる?
若いうちに家を購入するなら、最優先したいのが立地。将来、家族が増える、子どもが独立するなど、ライフスタイルの変化によって住み替える可能性も視野に入れて検討しましょう。駅近など利便性が高い立地や将来性のあるエリアなら、資産価値を維持しやすく売却時に有利です。
「最近は、オープンハウスの家から別のオープンハウスの家に住み替える人も増えています。『1軒目は3LDKの家を建てたけど、家族が増えたので4LDKに移り住もう』といったケースです。このように、立地が良ければ柔軟な住み替えも可能になります」(田所)
2. 水回り、その広さで足りる?
見逃しがちなのが水回りの使い勝手。住んでから「思ったより狭かった」とならないよう、ゆとりをもたせるのがおすすめ。家事効率を重視するなら、例えば寝室の広さを最小限に抑え、そのぶん脱衣所・洗面・洗濯スペースを充実させるのも一つの方法。洗濯、干す、たたむ、収納まで1カ所で完結できると、家事がぐっと楽に。
「もし自分が住むなら、水回りに一番こだわりたいです。家事は毎日のことだからストレスなくできる環境にしたいですし、干す場所、畳む場所、しまう場所がまとまっていれば暮らしの見栄えも良くなります。共働き家庭のお客さまからも、同じような声をよく聞きますね」(大野)
3. オプションは欲しいものを選べる?
標準仕様に追加する設備や機能などのオプションは、快適な暮らしやランニングコストの削減に大きく関わる重要なポイント。ハウスメーカーによって選べる種類やグレードに違いがあるので、事前に確認しておくと安心です。田所さんと大野さんが「自分なら絶対これをつける!」と教えてくれた、オープンハウスで人気のオプションはこちら。
- センサー付きダウンライト
人の動きを感知して自動点灯・消灯するライト。照明スイッチの操作や、「消し忘れた!」といった煩わしさから解放されます。使用時のみに点灯するため、節電・省エネ効果も。玄関や廊下、トイレをはじめ、家中のいたるところにおすすめ。
- ガス衣類乾燥機「乾太くん」
家事を時短したい人や、洗濯物を部屋干ししている人におすすめ。ドラム式洗濯乾燥機は乾燥中に洗濯できませんが、「乾太くん」なら洗濯しながら乾燥もできて、週末にまとめて洗濯したいときなどに便利。乾燥時間の短縮や除菌効果などのメリットも。

限られた土地を最大限に活かす設計力で、グループの成長を支える
オープンハウスの設計士たちは、都心駅近の狭小地という難条件に挑み、限られた土地を最大限に活かした快適な住まいを提供しています。その高い技術力と提案力の裏側には、設計職ながら数字を追う情熱と切磋琢磨できる環境がありました。家づくりの現場で自分の力を試したいと考える仲間をお待ちしています。