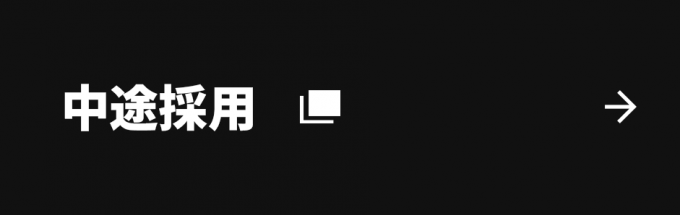大学院進学よりもオープンハウスを選んだのは、若手から活躍できる環境と社員の熱意に強く惹かれたから

製販一体を強みとするオープンハウスにおいて、設計部の手腕は重要なピースの1つ。若手のホープとして期待されてきた設計部の大塚さんは、入社6年目でグループ長に就任するほどの努力家です。業界的にもベテラン社員が担当することの多い設計部門で、若手から活躍するために必要な努力や信念、さらに異例のスピードで昇格した大塚さんならではのマネジメントの工夫や課題について聞きました。
記事サマリー
- 若手の設計担当でも、努力と対応力で期待値以上の信頼を得られる
- 大学院進学を止め、オープンハウスへ。インターン経験が人生を変えた
- 新人賞と年間MVPを獲得するほどの努力と才覚で、若くしてグループ長に就任
この記事に登場する人

大塚剛
建設事業部 設計部 課長。2018年に新卒入社。入社当初から設計部に所属し、注文設計に関わる。2023年に史上最短でグループ長に就任。新人賞、年間MVPなど、社内受賞歴も多い。
目次
「顧客の期待値をどれだけ超えられるか」が設計部の腕の見せどころ
―大塚さんが所属されている建設事業部は、オープンハウスにおいてどのような役割を担っているのでしょうか。
建設事業部は「家を建て、売る」というオープンハウスの中核事業を担う部署です。製販一体を強みとしている会社なので、土地の仕入れ、営業、設計、施工、お客さまへの引き渡しまで一貫して動くことが求められており、非常に重要な役割を任されています。現在はオープンハウスも戸建て以外の事業展開を盛んに行っていますが、それでも中核を担う部署として、ほかの事業部に遅れをとることは許されない、会社の成長に合わせて成長を続けねばならないという責任を感じています。
―建設事業部の設計部は、どのような業務を行う部署ですか。また、設計部が掲げるミッションがあれば教えてください。
設計部では、主に注文住宅と建売住宅の2本柱で戸建ての設計を行っています。私は入社以降、注文住宅の設計を担当しています。
お客さまが土地を購入されたあと、打ち合わせによってどんな家を建てたいかのご要望をお聞きし、それに沿った図面のご提案をするのが主な業務です。注文住宅の設計担当は、他社ではベテラン社員が出てくることが多く、オープンハウスのように若手が担当につくことはほとんどありません。そのため、いかにも経験のなさそうな若い設計担当が出ていくだけで、お客さまから敬遠されてしまうこともあるんです。それを熱量と知識量、そして対応力で納得いただくというのがオープンハウスの設計部の腕の見せどころ。プレゼン資料1つとっても、パソコンで立ち上げたものではなく、それぞれのお客さま専用に手書きでパースを書いたものをお持ちする、打ち合わせの場でお客さまのイメージをスケッチする。また、お客さまからご連絡をいただいたら可能な限り5分以内にお返事するといった細かい部分も含めて、すべてのお客さまに「特別感」を抱いていただけるよう意識し、当初の期待値をどれだけ超えられるかということをミッションにしています。
―大塚さんが設計部のなかで担っている職域や業務を教えてください。
私は現在、グループ長という立場を任されています。私自身もマネージャーを兼任しつつ、3つの設計グループの統括をする立場です。私の下に約10人の部下がいて、グループ全体で新規のお客さまを月に20件ほど担当しています。
先ほどもお話ししたように、私たちの仕事は土地を購入されたお客さまにご連絡をし、打ち合わせに伺って図面を提案することです。他社と異なる点を挙げるとすれば、設計部が営業的な役割も担うことでしょうか。ハウスメーカーによって違いはあれど、一般的にはお客さまとの打ち合わせは営業担当の社員が矢面に立ち、設計担当は裏で図面を用意するだけ、という場合も多いようですが、オープンハウスでは設計部の社員がメインでお客さまとやりとりをします。なので、私たちがお客さま宅などに出向いてお話しし、自分で引いた図面を持ってご提案したり、営業的観点から商品のご案内をしたりします。1件の打ち合わせ期間自体は3カ月程度ですが、メーカーとの調整や申請業務、建設中の現場での質疑応答なども任されているので、ただ図面を引いて終わりではない手応えがありますね。
―大塚さんは若くしてグループ長に抜擢されたそうですね。グループ長に昇格した現在の目標や、それを達成するために意識していること、努力していることなどはありますか。
2023年10月に、マネージャーからグループ長に昇格させてもらいました。グループ長になることを目標にしてきましたが、正直なところ自分がその立場になるにはまだまだだと思っていた部分もあります。今まで育ててもらったグループ長たちと肩を並べて働けるよう、早く追いつきたいというのが目下の目標です。
昇格して思うのは、もはや自分は個人ではなく、会社側の立場で考えなければならないということ。プレイヤーのときは1人のお客さまに都度向き合えばよかったのが、今はグループで担当するお客さま、そしてひいてはオープンハウスのすべてのお客さまに対して責任を持ち、幸せになるお手伝いをさせていただくという気概で励んでいます。そのためには、自分が課題に対してすぐに動ける能力を身につけることに加え、部下の育成や教育も重要になります。特にオープンハウスは入社1〜3年目の社員がほぼ主戦力になりますから、若手をいかに戦える人材にしていくかという視点も重視していきたいですね。

大学院進学の決断を覆した、オープンハウスのインターン経験
―大塚さんご自身も新卒として入社し、即戦力になることを求められたと思いますが、ご苦労もあったのではないですか。
私のときは4月に入社後、ゴールデンウィーク明けにはもうお客さまの担当としてデビューしました。当時は……そうですね、恐怖しかなかったです(笑)。それまで先輩や上司の打ち合わせに何度も同席し、知識としては何をすべきかわかっているのに、実際にやってみたときに何もできないもどかしさがあったのをよく覚えています。
それでも周囲が適宜フォローしてくれましたし、実地で鍛えられるのが成長の近道だというのも理解できたので、がむしゃらに頑張りました。「お客さまのために自分ができること、自分の強みはなんだろう」と考えて、手書きでイメージ画を描いたのもそのときからですね。お客さまが喜んでくれることならなんでもしようと試行錯誤した結果、最初に担当したお客さまに受注いただけて、その後もよい関係を築けました。
―カスタマーサービス部が掲げているミッションを教えてください。
顧客満足度をアップさせるためには、お客さまの声に対してその場だけで対応するのではなく、問い合わせの根本を潰し、再発しないようにする必要があると考えています。そのためにカスタマーサービス部が取り組むべき軸として「情報の集約」、「顧客への対応品質の統一」、「スピード感のある対応」の3つがあります。まだ取り組み始めたばかりですが、まずはお客さまからの問い合わせをカスタマーサービス部に集約して蓄積し、誰が対応しても同じようにできるよう、対応品質とスピードを向上・統一していくことをミッションとしています。
―設計担当として必要な知識はどのように学んでいくのでしょうか。
私は大学の建築学科を出ているのですが、大学の授業で題材となるのは大規模な公共施設などが多く、一般的な住宅を建てるための知識のほとんどを入社後に学びました。現在行っている研修ベースでお話しすると、入社後半年ほどは座学で知識を蓄える期間があります。メーカーさんをお呼びしてお話を聞くこともありますね。同時に、お客さまとの打ち合わせなど、日常的に必須の業務はロールプレイング形式で研修を行います。こうした研修を受けながら上司や先輩について現場にも同席し、実地と研修で知識を深めていくことになります。また、オープンハウスは入社前の1月にすでに配属が決まっており、入社前から見よう見まねで図面を引いたり、ロールプレイングをさせてもらったりできるので、それも実践力を培うための経験になります。
今はおおよそ6月末くらいから、マネージャー同席の元で設計担当としてお客さまを任せています。1年目は毎回上司のフィードバックを受けながら進め、翌年の年明けくらいからだんだんと独り立ちして2年目を迎えるような感じです。これは業界的には驚異的なことで、こんなに早く独り立ちしてバリバリ働けるのはオープンハウスくらいですね。すぐに即戦力として扱われるプレッシャーはもちろんありますが、1年目からお客さまを持てることは何よりの喜びですし、大きな責任を伴う緊張感が「働いている!」という充実にもつながります。
―そもそも、大塚さんはなぜオープンハウスに入社しようと思ったのでしょうか。
大学3年生の時に、オープンハウスのインターンに参加したのがきっかけです。とはいえ、当時は就職する気はまったくなく、就職活動の練習というか、社会勉強くらいの気持ちでした。将来的に大手設計事務所への就職を希望しており、入社するには院卒が必須条件だったこともあって、当たり前のように大学院に行くものだと思っていました。
しかし、オープンハウスでの経験はその固定観念を覆すほどのものでした。ほかにもいくつかの企業のインターンを受けたのですが、オープンハウスは圧倒的に「人」が違いました。他企業では、インターンと接する社員はほとんど人事部の方のみ。でもオープンハウスは実際のオフィスで5日間、チーム制で設計を競う業務が与えられ、実際に働いている社員の雰囲気を感じながら体験ができました。インターンが終わる頃に「自分はなぜ大学院に行きたいんだろう」、「なぜ大手設計事務所に入りたいんだろう」と考えたとき、それが見栄や体裁のような漠然とした気持ちだったことに気づいたんです。さらに、そうした事務所では20〜30代は下積みでアシスタント業務をするのが通例で、設計担当になれるのは30代半ば〜40代から。一方、オープンハウスならすぐに戦力になれることにも思い至り、自分のキャリアと適性を考えた結果、この部活動のような熱くて勢いのある会社に入りたいと心が決まりました。
オープンハウスに入社すると報告したとき、大学の教授からはかなり引き止められました(笑)。本当にいいの、と何回も言われましたが、自分の決めた道に進みました。大きな分岐点でしたが、あのときの決断は運命的なものでしたね。
―オープンハウスで設計の仕事をするなかで、印象的だったエピソードがあれば教えてください。
どのお客さまも印象的で忘れがたいのですが、よい経験になっているのは多様な価値観を持つお客さまとのお仕事です。特に外国の方は、日本人とは異なるルールに則って生活されていることがあります。たとえば中国の方なら風水を重んじていることも多く、水回りや火を使う場所の方角などにこだわりがあるのはもちろん、寝室の上に汚水を流す配管を通してはならないなど、構造面に関わるオーダーをいただくこともあり、その都度工夫を凝らして対処しました。
また、ある欧米の方からは「各居室にバス・トイレを付けたい」というご要望をいただいたものの、土地の広さは限られています。そのときはいったんすべての要望を汲んだ間取りをお見せして現実的かどうかを実感していただき、バスルームを主寝室の側に設置することでご納得いただきました。若いうちからこういった経験が積めるのもオープンハウスならではですね。

▼建築技術職への応募フォームはこちらから
新卒採用の方はこちら 中途採用の方はこちら
新人賞と年間MVPのW受賞。最短で念願のグループ長へ
―入社以降、表彰される機会が多かった大塚さんですが、その裏にはどのような努力があったのでしょうか。
いろいろな方の指導のおかげで、入社1年目のときに新人賞を獲得しました。その半年後に、注文設計の部署全体でランキングされるオプション受注額の年間MVP(1年目の10月〜2年目の9月)をとりました。自分で言うのも僭越ながら、歴代トップ金額を出せたので鼻が高かったです。
トップになるのはやはり大変なことでしたが、せっかくやるなら上を目指してやろうと思って、まずは目標設定から始めました。歴代の新人賞やMVPの実績から、ここまで数字を積めば1位を狙えるだろうという目標額を算出し、その数字の1.5倍、2倍を目指して模索する日々でした。もちろんオプションを受注いただけるかどうかはお客さまの状況や要望にもよるので無理な営業はできませんが、オプションを売るのではなく、お客さまの夢を叶えるための提案を心がけたんです。潜在ニーズを引き出して提案すると、お客さまから信頼いただけますし、その信頼から受注いただくことも多かったですね。
―そのような実績が評価されて、現在のポジションにつながっているんですね。
そうですね。年間MVPを受賞したあと、事業部では最短の2年目の10月に主任の役職をもらい、3カ月後にマネージャー、そして昨年グループ長に就任しました。
年齢や年次に関係なく、努力を評価してもらえるのは嬉しい反面、プレイヤー期間が短いだけに部下への接し方などは苦労した部分もあります。プレイヤーのうちは「自分ができたか、できなかったか」というシンプルな評価軸だったものが、マネージャーになるとそうはいきません。自分ができたことが部下にはできないケースがあると理解するのにも時間がかかりましたし、それをどう指導するかのコツを掴むのにも難儀しました。褒めたほうがよい社員もいれば、自分のように叱咤して伸びる社員もいる。若手が多いからこそ、長所を伸ばして同じ方向を向かせることを意識しつつ、今も悩みながら指導にあたっています。
―社員教育やマネジメントにおいて、大塚さんが心がけていることはありますか。
私はほかのグループ長よりも若いので、経験が浅いことがウィークポイントである一方、部下と年が近いというメリットもあります。元来おしゃべりな性格というのも手伝って、ふらっと部下の席まで行って雑談をしたり、隣に座って気楽に話を聞いたりしています。どこかの工程で行き詰まっている部下がいれば、その要因にはどんなことがあるのかを細分化し、どんなフォローが必要なのかを聞き出し、分析する必要があるので、こうしたコミュニケーションは大切ですね。
教育にしろマネジメントにしろ、その大きな目的はお客さまに喜んでいただくこと。そしてその先に会社の成長があります。部下と接し、アドバイスをするうえでも、どうすればお客さまのためになるかを軸に伝えていくことで、部下自身が課題や解決策にたどり着いてくれることも多いです。ある程度は部下を信頼して任せてみたり、チームのなかで役割を決めて主体的に進めてもらったりすることで、チームの一体感が出てきたように思いますし、そしてそれが数字にも現れてきていると感じています。

失敗はすぐに成功体験で塗り替えることができる
―大塚さんが考える、オープンハウスの「よいところ」を教えてください。
年次に関わらず、社員がチャレンジする機会を何度も与えてくれるところですね。失敗した直後でもすぐに再チャレンジの場を設けてくれて、失敗を成功体験で塗り替えられるのが、オープンハウスの成長の秘訣かもしれません。「挑戦して成果を出したい」、「自分を試したい」という人にとって、とてもよい環境だと思います。
―では、設計部にはどのような人材がマッチすると思いますか。
設計部の場合、お客さまの前に出るには建築士という資格が必要なので、やはり建築学科を卒業していることが必要になります。そうでない仕事もありますが、設計部はほとんどの社員が建築学科卒業ですね。
設計部はもちろん、オープンハウス全体に言えるのは「素直な耳を持つ人」であるということです。言われたことを素直に受け止めて、それをすぐ実践できる人は伸びが早いし、結果を出していると感じます。あとは、人が嫌がる仕事にさっと手を上げて、すぐに飛びついていく人。ほかの人ができない仕事ができますし、周囲が次に仕事を頼みたくなるのでどんどんチャンスを掴み、経験が積めます。そういう人材は重宝され、オープンハウスでもより上へ行けるのではないでしょうか。
―最後に、入社を希望する方に向けてメッセージをお願いします。
私が入社を決意した理由もそうですが、ほかの会社にはない熱量や風土はとても魅力的です。それから、やはり特徴的なのは経験を積めるスピードの速さ。大学の同期は多くが大学院に進学し、設計事務所などに入社していますが、まだまだ新人扱いです。私がオープンハウスに入社すると決めたときは否定的だった彼らも、今の私のポジションと任されている仕事のレベルを知ると、尊敬のまなざしを向けてくれます。自分が何をしたいのか、数年後にどんな自分でいたいのかのビジョンを明確に持ち、後悔のない選択をしてほしいと思います。

経験がモノを言う設計業界で、若手の熱量と努力が花開く会社
オープンハウスに入社後、エースとして出世街道を歩んできた大塚さん。持ち前の人懐っこさと膨大な努力によって現在のポジションを得て、会社の成長に向けて自分とチームを鼓舞し続けています。大塚さん自身が体現しているとおり、オープンハウスでは努力次第で若手のうちから活躍することが可能。誰よりも早く成長し、戦力になりたいと考えている方は、ぜひオープンハウスでのビジョンを描いてみてください。